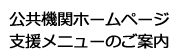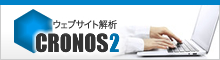高齢者・障害者の携帯電話利用に関するアンケート調査
主な調査結果
主な調査項目について、結果を文章もしくはグラフ・表形式で紹介します。
主な調査結果一覧
携帯電話を利用しはじめたきっかけ
家族や友人・知人と頻繁に連絡をしたいから(10人)、メールがしたいから(10人)公衆電話が少なくなったから(9人)といった理由が多い。その他の内訳としては「緊急時の連絡手段」を挙げた人が多かった。
グラフ1:携帯電話を利用しはじめたきっかけ 【グラフ1の拡大と説明】
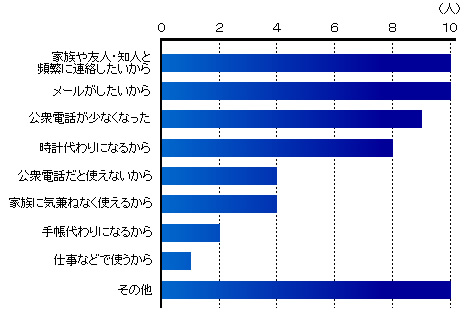
利用用途
一番よく利用する機能として、20人中12人がEメールと回答。音声通話は6人であった。
| 利用する機能 | 人数 |
|---|---|
| Eメール | 12人 |
| 音声通話 | 6人 |
| ショートメール | 1人 |
| 時計 | 1人 |
利用することがある機能やサービスは下図の通り。オサイフケータイや音楽再生の利用率は低い。
グラフ2:利用用途【グラフ2の拡大と説明】
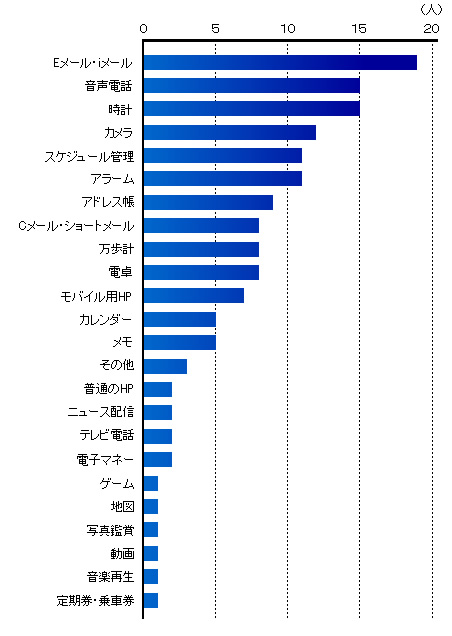
携帯電話の利用頻度
20人中12人が一日に何度も利用している。一方で、月に数回通話をする程度、という人もいる。
| 利用頻度 | 人数 |
|---|---|
| 一日何度も利用 | 12人 |
| 毎日利用 | 4人 |
| 週に数回程度 | 2人 |
| 週に一回程度 | 2人 |
携帯電話でのホームページ利用
携帯電話でホームページを閲覧している人は20人中7人であった。
よく利用するのは時刻表・乗り換え案内(5人)、天気予報(4人)などの情報系コンテンツ。ショッピングやオンラインバンキングの利用者はいなかった。
グラフ3:携帯電話でのホームページ利用【グラフ3の拡大と説明】
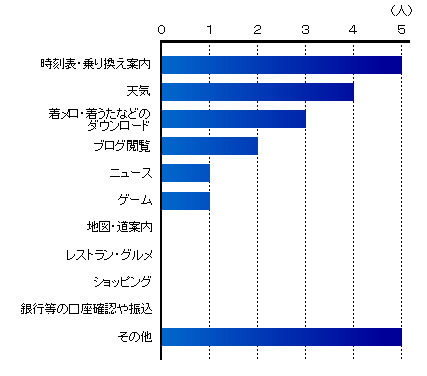
携帯電話でホームページを利用していて困ること
操作性の問題の他、料金や個人情報の管理についても不安を感じている。
グラフ4:携帯電話でホームページを利用していて困ること【グラフ4の拡大と説明】
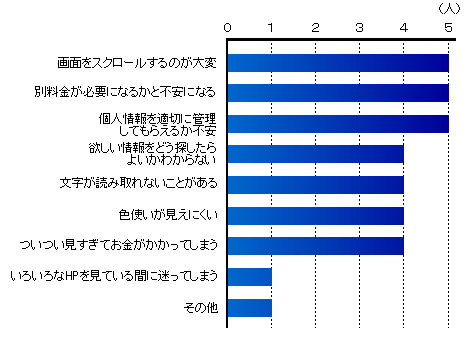
携帯電話を利用するようになったことによる日常生活の変化
回答者の多くが、コミュニケーションの頻度や相手が増えたと感じている。また、外に出る機会が増えた(全盲、聴覚障害)、どこにいても家族と連絡が取れるので安心感が増した(全盲)といった効能も挙げられている。
グラフ5:携帯電話利用による日常生活の変化【グラフ5の拡大と説明】
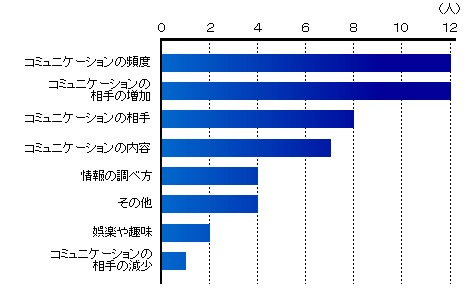
自由記述のコメント(抜粋)
- 息子夫婦と孫の情報を写真つきでメールしてもらえるようになった
- 普段なかなか話す機会が少ない他の学校の友達とメールできるようになった
- 滅多に電話しなかった旧友の交流の頻度が増した
- 携帯を勝手から連絡がとりやすくなり、詳しく打ち合わせもできるため、友人と会う機会が増えた
- 外出時にいつでも家族などに連絡ができるという安心感は大きい
- 同じ聴覚障害者とのコミュニケーションが増えた
- 一方的に伝えるだけだったが、メールやテレビ電話の利用により会話がスムーズになった
- 電話を使えない相手と気楽にやり取りできるし、周りを気にせずに利用できる
- 家の中で、パソコンの前に座っている生活から、外に出て色々な団体の集まりに参加したり、音声付き映画を見るなど、外に出る機会が大幅にアップした。
使っていない携帯電話の機能
| 機能 | 人数 |
|---|---|
| テレビ電話 | 14人 |
| 普通のホームページ | 13人 |
| モバイル用ホームページ | 11人 |
| Cメール・ショートメール | 9人 |
| 音声電話 | 5人 |
| 電卓など文房具的な使い方 | 5人 |
| 写真 | 4人 |
| カレンダー | 3人 |
| その他 | 3人 |
| Eメール・iメール | 2人 |
| 時計 | 1人 |
携帯電話を利用していて困ること
最も多かったのは「有料サービスか無料サービスかわかりづらい」という点で、20人中17人が挙げている。
グラフ6:携帯電話を利用していて困ること【グラフ6の拡大と説明】
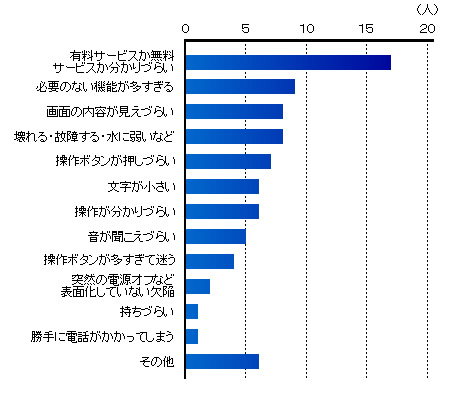
携帯電話の機能の認知状況
| 機能 | 人数 |
|---|---|
| 待ち受け画面の変更 | 20人 |
| 文字を大きくできる | 19人 |
| 留守電 | 17人 |
| 短縮ダイヤル | 17人 |
| ボタン音を消せる | 15人 |
| 表示が変えられる | 14人 |
| 音声メモ | 13人 |
| キー操作無効 | 12人 |
| アクセス制限 | 12人 |
| 特定の相手を簡単に通信 できるように設定できる |
12人 |
| アドレス帳の検索方法が変えられる | 11人 |
| メニュー画面のカスタマイズ | 9人 |
| ジャンプ機能 | 4人 |