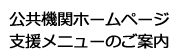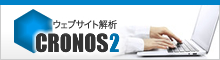第14回「迷いやすさを解消し、探しやすく伝わりやすいサイトを目指す」~リニューアル準備の取組と、その先を見据えた検討~
[ 2025年11月21日 ]
ゲスト
公立大学法人岩手県立大学 企画・広報室 主査 大橋 健介さん
主査 阿部 いづみさん
学内で議論を重ね、利用者視点でわかりやすいメニュー名称を選択
岩手県立大学ウェブサイトの前回のリニューアルでは、情報分類の根本的な見直しは行われませんでした。特に入試情報に関しては、課題が山積みだったようです。
アライド:現在の大分類「入試・高大連携」はどのような経緯があるのでしょうか。
岩手県立大学:令和3~4年度にかけて、現在の形に見直しました。その前は今よりもっとわかりづらかった状況で、当時、宮城大学がグッドデザイン賞を受賞された時期でしたので、参考にしました。
そのときは、見た目のデザインを重視して見直しを行いました。それでも、試験の時期が近づくにつれて、掲載するPDFの数が増えてきて、年度末頃になると見づらくなってしまいました。そこも次回のリニューアルでは改善したいと思っています。
アライド:アンケート等で「入試情報が探しにくい」という意見が多かったそうですが、見直しに向けてどのような検討をされましたか。
岩手県立大学:見直しに向けた検討では、「高大連携」や「入学者選抜」など、使用する名称について議論がありました。学内からは、「正式名称を用いたい」「高校だけではなく、小中学校とも連携している」等、様々な意見がありましたが、全ての意見や思いをタイトルに反映していくと、リンクタイトルがどんどん長くなり、視認性を欠いてしまう恐れがありました。何度も議論を重ねて、一般の方にとってわかりやすい名称にしよう、という方向に落ち着きました。
アライド:サイトを利用する方が直感的に探しやすいことを重視して、タイトルを設定したのですね。

大橋 健介さん
各グループと協力して、情報分類の根本的見直しに取り組む
アライド:情報分類の見直しは大分類ごとに行われました。各グループとのやりとりで大変だったことはありますか。
岩手県立大学:どのグループも自分ごととして考えて対応していただいたと思います。例えば、入試情報は、令和3年度に項目の見直しを行っていて、その構成を継続したいか、見直したいか、という観点で検討しました。次回のリニューアルで大きく変わる部分として、学部・短大・大学院という、区分別にメニューを設けることにしています。その方針についても特に反対意見は出ませんでした。
グループによって、ウェブページの習熟度合に違いがあります。企画・広報室からの依頼に対してスムーズに取り組める場合もあれば、全くわからない、という場合もあって、そこの苦労はあったかもしれません。
しかし、サイト自体に対する問題意識がある人が多く、「改善したほうが良いのだろうな」という思いを持ちながら、忙しい中取り組んでいただいたと思います。
アライド:各グループとの具体的なやり取りはどのように行いましたか。
岩手県立大学:Excelの表で情報分類を表して検討に使用しました。普段見ているサイトの構造や階層などをイメージしやすくなったかもしれません。
ただ、検討内容のやりとりは大変でした。
例えば大分類「大学案内」は現行から大きく変更する必要がないためスムーズに進行できましたが、「学生生活」は、ページを探す際にぐるぐる迷ってしまうことが多く、見直しに苦労しました。
現在公開している改善前のウェブサイトでは、パンくずリストが情報構造を表せていない箇所が多々存在しており、そのとおりに行ってもたどりつけないことがありました。学内関係者がわからないということは、受験生にとってはもっとわからないはずです。少子化が進む中、本学への志願者を確保していくために、ウェブサイトをわかりやすくしなければ、という思いです。
当事者意識を持って、リンク切れ、アクセシビリティ等の改善に対応してもらうには
アライド:アクセシビリティの改善や、リンク切れの解消は、どのように取り組まれましたか。
※岩手県立大学は令和5年度にウェブアクセシビリティ方針を公開している。
岩手県立大学:アライドさんから問題のあるページのリストを提供いただいて、例えば代替テキストに問題があるものは、企画・広報室で修正案を用意して、それを担当部局に見てもらいました。問題がなければ、現行の運用保守業者にリストを送って修正作業をお願いしました。
リンク切れも同じような流れですが、このリンクは削除するとか、ここにつなぎ直してほしい、というのは、部局に照会しないといけなかったので大変でした。企画・広報室で対応できる部分もあったのですが、やはり確認してもらって当事者意識を持っていただくのが大事かなという考えもありました。
アライド:それは本当に大事なことですね。全て「企画・広報室さんに任せておけばいいか」という文化になってしまうと、組織全体として質の良い情報発信をしていく体制が生まれにくくなりますよね。
岩手県立大学:職員が自分達で記事を作成して運営しているサイトなので、主体的にやらなきゃいけないことを思ってもらうために、なるべく部局を巻き込んで取り組みました。
アライド:その反応はどんな感じだったのでしょうか。
岩手県立大学:公開ページの修正の部分は、量の多さに驚く方も正直いたと思います。しかし、みなさん真摯に取り組んでいただきました。
アライド:2025年9月に、アクセシビリティに関する職員研修を初めて実施しましたが、いかがでしたか。
岩手県立大学:そうですね。前回のリニューアルでは行いませんでした。障がいのある方がどのようにウェブサイトを見ているか、また、音声読み上げソフトでページがどのように読まれるか、リアリティを持って知ることができました。そういう現実を知ることによって、アクセシビリティ対応の必要性が伝わったと思います。
大学全体の広報方針に基づき、デザインの検討が進行中
アライド:現在進行中のことをお伺いします。リニューアル業務を担当している事業者さんとトップページデザインを検討中ですね。
岩手県立大学:大学としての広報方針・広報戦略を広報部門全体で検討しており、その方向に合うようなサイトを目指しています。人の温かさ、親しみやすさのような色が出るデザインを事業者に要望として伝えています。
入学案内や広報誌等の冊子を制作する事業者が、2年ごとに入れ替わっていたため、デザインも2年ごとに変わってしまう状態でした。大学全体のブランディングに関わる部分で、岩手県立大学のイメージが定着しづらいという問題意識がありました。
アライド:岩手県立大学として目指す方向性というのはどのようなものでしょうか。
岩手県立大学:本学は、「実学実践」を重視していて、近隣の岩手大学や東北大学とは異なる系統で学部を構成しています。岩手県立大学のイメージを確立する必要があるという考えのもと、ブランディングの戦略を考え始めました。その一つとして、広報物のデザインを見直そうという動きがあります。それと並行して、ウェブサイトの様々な課題も改善しながらリニューアルしようとしています。
大学の中期計画に、大学のブランド力の向上や、ウェブサイトの刷新を盛り込んでいます。令和10年度は開学30周年の年でもあるので、そこに向けて取組を進めています。
アライド:大学らしさをデザインで表現することについて、検討を重ねてこられた内容が、活かされているのですね。

岩手県立大学正門
リニューアルの先を見据えて検討していくこと
アライド:現在取り組んでいらっしゃるリニューアルでは、情報が整理された探しやすいウェブサイトとすること、アクセシビリティを改善することを目指されていると思います。これらは、情報がきちんと伝わるウェブサイトとするうえで、最優先で対応すべきことだと思います。その先の取組について、議論されていることはありますか。
岩手県立大学:現在取り組んでいるリニューアルは、優先度の高い問題や課題を解決して、最低限のスタートラインに立つという段階だと認識しています。今後、志願者を確実に確保すること、大学としての認知向上・強化が、大きな課題です。
SNSで発信しているのですが、最も足りていないのは、「大学で行っている様々な活動を知ってもらう」という部分だと思います。どのようにお知らせしていけば良いのか、考えなければいけません。
例えば、地域連携を強みとして掲げているので、研究の成果や地域との関わりについての広報を、人手が少ない中でどのように体制を組んで取り組んでいくか、考えていかなければならないと思っています。
アライド:学生の声を活かそうという取組がありますか。
岩手県立大学:ブランディングの事業をスタートした際に、学生向けのワークショップを行い、「県立大学らしさって何だろう」と学生に話してもらいましたが、協力してくれる学生さんや、県大を好きな学生さんがたくさんいることを、あらためて認識することができました。
アライド:魅力をアピールするコンテンツを企画しても、更新が大変で続かなかったりする場合があります。どのように魅力を発信したら良いか、学生や受験生になり得る年代の方々の意見を確認する取組は今後も重要になってくると思います。
アライド:学部ウェブサイトは、本体の公式サイトリニューアル実施後に、段階的に改善作業を行う計画と伺っています。現在取り組まれていることはありますか。
岩手県立大学:各学部に向けて、学部サイトの運用に関するアンケート調査を行い、現在の学部サイト運用について率直な意見を回答してもらいました。特設サイトがどのくらいあるのか整理して、それらは今後も独立して運用していくか等を確認する必要があります。そのうえで、学部の魅力アピールにつながる検討ができないか、考えていきたいと思っています。

学生とのワークショップの様子
担当者が変わっても、目標に向かう検討を継続できるように
アライド:来年度のリニューアルに向けた準備と、リニューアルの先を見据えた将来的な課題の検討を同時並行で取り組んでいく大変さがあるように思います。
岩手県立大学:「リニューアルが終わってから検討しよう」と決めてしまうと、恐らく将来を見据えた課題検討に着手できないので、今から細々とでも議論していくことが重要だと思っています。結果的に対応できないものが出てくるかもしれませんが、議論の芽は残しておいて、リニューアル公開以降にアンケートやインタビューを実施してから再度検討する、という方法もあるかもしれません。
組織としては人事異動がありますが、人が変わったら検討が終わるということになるともったいないので、関わるメンバーが変わっても、目標に向かって検討を継続できるような体制を今から作っておくことが大事だと思います。
アライド:大学に限らず、どの団体にとっても重要なことですね。
令和8年度に予定されているリニューアルと、リニューアルの先を見据えた取組についてお話をお伺いしました。本日は貴重なお話をいただきありがとうございました。

企画・広報室の大橋さん、阿部さん